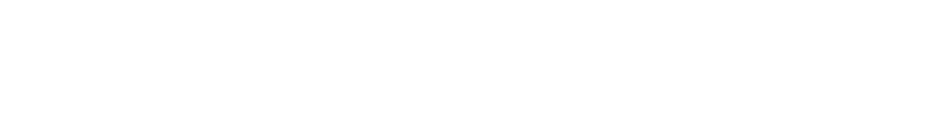- HOME>
- 親権問題
親権者の指定

未成年の子がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。これを後日に決めることはできません。この時、夫婦の共同親権とすることはできません。必ず夫婦の一方、つまり、父親または母親のどちらかが親権者となります。
夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、協議離婚もできません。離婚の調停や裁判で親権者を定めることになります。
また、未成年の子が数人いる時は、その全員について親権を決めなければなりません。
親権とは
親権とは、わかりやすく言うと、親が未成年の子供を、一人前の大人に育てるという責任・役目と言えます。親権は、権利という言葉になっていますが、義務でもあります。
なお、親権には、①子供を監護教育していく権利ないし義務(民法820条)と、②子供の財産に対して管理処分していく権利義務(民法824条)の2つの側面があります。
両親が離婚する場合の親権
前提として、両親が結婚している間は、父母が共同で親権を行っている状態です。
両親が離婚する場合、離婚後は父親か母親のどちらかが一人で親権を行います。結婚中のように共同親権のままにすることはできません。
また、離婚後の親権者が決まっていない状態では離婚届は受理されず、離婚は成立しません。
離婚後の親権者の決め方
夫婦の話し合いで決める
夫婦のどちらが離婚後の親権者になるかは、夫婦間の話し合いで決めることができます(協議)。
この場合は、話し合いで決めた親権者を離婚届に記載し、提出し、それが受理されると、離婚届に記載した親権者がそのまま戸籍上の親権者になります。
親権者の記入は慎重に行う必要があります(協議離婚の場合)
親権者は離婚届に記載した通りに戸籍に記入されてしまいます。
とにかく離婚届を受け付けてもらいたいがために、あるいは、夫婦間の離婚の話し合いの雰囲気に圧倒され、納得できないままに離婚届けに夫婦のどちらかを親権者として記載してしまう、という方もおられます。
しかし、離婚後に、親権者を変更することは、相手が同意している場合以外には、極めて困難です。
親権者をどちらにするのか、という問題は、慎重に、冷静に話し合って決定する必要があります。また、親権者の指定を裁判所が判断した場合には、どうなるのか、という点も念頭において話合う必要があります。
裁判所が親権者を指定する際に考慮する事情 (裁判所において親権者を定める際の基準)
(1)それまでの子供の監護・養育の状態がどのようなものであったか、という実績が重視されます。
これは、現在、子供の生活・監護状況が安定しているのであれば、現在、子供の面倒をみている方(監護している者)と子供との結びつきを尊重すべきであり、この状況をあえて変更させる必要はなく、また変更させることは適切ではない、という考えによります。
但し、別居している子供を、無断で連れ去り、以後、子供との生活を続けたという場合は、安定した監護状況が続いたとは認められない傾向にあります。
(2)子供が幼い場合には、母親が優先される傾向にあります。これは子供の監護・養育に際して母親のほうが、子供に緊密な関係にある場合が多いためです。つまり、父親と母親を比較すると、母親のほうが子供の面倒を良くてみてきたという場合が多いためです。
(3)子供の意思も考慮されます。特に子供が満15歳以上であれば、必ず子供の意見を聴かなければならないこととなっています。
満15歳に満たない子供でも、概ね10歳前後になれば、意思を表明する能力があると思われますので、子供の意思は、親権者を定める際に、重要な要素となっていきます。
(4)このほか、子供の監護・養育能力を考慮することはもちろんです。
さらに、他方の親(子供と別居することになった親)と、子供との面会交流を許容することができるかどうか、も問われることがあります。
兄弟姉妹は分離するべきではない(特に子供が幼い場合)という考えもあります。
裁判所では、このように、様々な事情・要素を考慮して、子供の福祉を実現する観点から、親権者を定めることになります。
親権者の指定は、あくまで子供の福祉・利益は何か、という問題です。従って、夫婦間でトラブルになっている状態ではありますが、相手を攻撃するなど、夫婦で子供の取り合いをしているかのような状態となることは、絶対に避けなければなりません。
そして、親権者は、離婚によって父母のいずれか一方となりますが、離婚後も、双方(父母)が子供の養育に協力し合うという姿勢を崩さないことが重要です。
つまり、調停であれば、家庭裁判所の調停委員は、このような観点から当事者間の話合いをまとめようと努力します。
訴訟であれば、このような観点から、裁判所が判断して親権者を指定します。
離婚後の親権者になったら
子供との関係
ご自身が親権者となった場合、子供との関係性は離婚前と基本的に変わりません。
引き続き、子供の世話や教育をする役割(身上監護権)と、子供の財産を管理する役割(財産管理権)を行います。
元パートナーとの関係
元パートナーとの間で面会交流についての取り決めがある場合、親権者はその取り決めに従って、子供と元パートナーとが会うことを認めなければいけません。
詳しくは、『面会交流』のページをご参照ください。
離婚により、親権者でなくなったら
子供との関係
離婚により親権者でなくなった親は、原則として子供と暮らすことができなくなり、また、子供と会う、手紙やプレゼントのやり取りをするなどの交流を自由にすることができなくなります。
一方で、親権者でなくなったとしても、親子であることは変わりませんので、養育費を支払う義務(この立場からすれば扶養義務)は残ります。
お気軽にご相談ください
一度親権者を決めてしまうと、離婚後、これを変更することは極めて困難になります。お子様のためにも、くれぐれも慎重にご検討ください。
親権でお悩みの方は、お早めに弁護士までご相談ください。