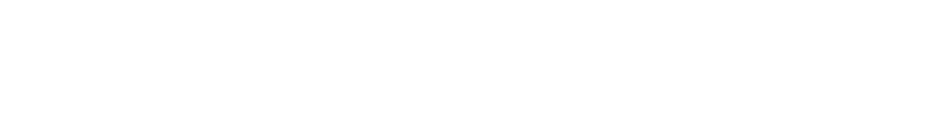- HOME>
- 財産分与
財産分与とは

財産分与とは、離婚する際に夫婦が築き上げてきた財産を公平に分配することです。財産分与には、以下の3つの要素がありますが、その中心は①の清算的要素です。
また、この3つの要素のほか、あるいは婚姻中の夫婦共同財産の清算の一環として、過去の婚姻費用(生活費負担)の清算という趣旨も含まれる場合があります。
財産分与には次の3つの要素があります。
- ①婚姻中の夫婦共同財産の清算
- ②離婚後の弱者に対する扶養料
- ③離婚による慰謝料
中心は、①婚姻中の夫婦共同財産の清算です。また、夫婦共同財産の清算の一環として、過去の婚姻費用(生活費負担)の清算という趣旨が含まれる場合もあります。
財産分与の対象
離婚の際には、名義に関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります。
これには、共有財産と実質的共有財産の2つがあります。
共有財産とは、共有名義のマイホームなど結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産です。
結婚後に購入した家財道具などもこれに含まれます。
実質的共有財産とは、預貯金、株、不動産、自動車など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち、夫婦の一方の名義のものです。
また、つい忘れがちですが、生命保険や学資保険も。夫婦共有財産となります。
さらに、退職金 については、実際に退職金の支払いを受けるのは将来の退職時ですが、まだ払われていない段階でも、一種の積立金に類する財産として理解され、財産分与の対象になります。また、将来の 企業年金も、財産分与の対象になりえます。
尚、結婚前に築いた財産や、婚姻中に相続で取得した財産などは、特有財産と言い、財産分与の対象となりません。
どの時点の財産が対象となるのか(基準時)
財産分与は、婚姻中の夫婦共同財産を清算することが中心となることから、夫婦の協力関係が終了したとき、つまり別居開始時の財産を対象とするのが通常です。
財産分与の割合の決め方
財産分与の割合は、原則として夫婦が 5:5 で分け合う「2分の1ルール」が定着しています。結婚後の財産形成への貢献度は、原則として、夫婦で同等のものと考えるわけです。
住宅ローン支払中の自宅不動産をどうするのかといった問題は、住宅ローンの残額と自宅不動産の査定額を比較して検討するなど、個別の事情によるところが大きいと言えます。
上にも述べましたように、自分名義の財産だから自分のもの、という訳ではありません。考え方としては、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まる、とされています。
財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題ですが、通常は2分の1ずつの貢献と考えます。
しかし、次のような場合は例外となり、2分の1ルールよりも増減する可能性があります。
- 夫婦に同居していない期間が存在している場合
- 協力扶助義務の分担状況に大きな不均衡がある場合
- 夫婦の一方が著しい浪費によって夫婦共有財産を減少させていた場合
- 夫婦財産契約(婚前契約)で財産分与の割合が取り決められていた場合
- 夫婦の一方が特別な資格や能力により高収入を得ていた場合(プロスポーツ選手など) など
夫婦の債務・借金の精算
もし、プラスの財産がなく、夫婦が結婚生活を営むための債務・借金しかない場合には、清算の対象となる財産がない、として、財産分与請求権はありません。
プラスの財産と、債務・借金の両方がある場合、プラスの財産から債務・借金の額を差し引いてプラスになれば、そのプラス分に対して財産分与請求権をもつことになります。
もし、プラスにならないのであれば、債務・借金のみの場合と同様に、清算の対象となる財産がなく、財産分与請求権はありません。
もっとも、夫婦間で、債務・借金の負担割合を協議して、合意することは可能です。調停(財産分与調停または離婚調停)においても、このような合意は可能です。
財産分与請求権がないようなケースでも、将来、元の夫婦間で、債務や借金の負担をめぐって、財産分与とは別の理屈で紛争となる場合もありえます。そこで、債務・借金の分担などは、離婚や財産分与の調停などにおいて協議をして解決しておくことをお勧めします。
将来給付される退職金について
将来給付される退職金は、財産分与の対象となるのが通常です。
財産分与は、離婚する際に夫婦が築き上げてきた財産を公平に分配するものです。
将来給付される退職金については、一般に、基準時における退職金の額のうち、婚姻期間に対応する額が財産分与の対象となります。離婚時にまだ支払われていない場合でも、財産分与は離婚時の清算であるから、離婚時に支払うべきことになります。
退職金の取扱いについては、原則はこのようになりますが、様々な考え方もあり、また、個別の事情が考慮されることもありますので、分与すべき金額や、これを支払う時期については、ケースバイケースとなることもあります。
マイホームと住宅ローンの扱い
結婚後に購入したマイホームは、夫婦の共同名義か、どちらか一方の名義かにかかわらず、財産分与の対象になります。
反対に、夫婦のどちらかが結婚前から所有しているマイホームは、持ち主の特有財産であり、財産分与の対象にはなりません。
マイホームが財産分与の対象となる場合
夫婦のどちらかがマイホームに住み続けるか、売却してその売却額を分割するか、夫婦間で協議し、決めます。
マイホームが夫婦どちらかの特有財産である場合
原則として、離婚後もマイホームの名義人、ローンの名義人などは変わりません。
夫婦間の合意により名義人を変更することも考えられますが、名義の変更には住宅ローンの債権者(銀行など)の許可が必要な場合があります。
また、マイホームの名義が夫婦の一方からもう一方へ移ったとしても、それにより住宅ローンの支払い義務まで一緒に移動するわけではありません。
離婚後のローンの支払い
マイホームが財産分与の対象になる場合、残った住宅ローンをどうするかについても考える必要があります。
マイホームを売却する場合
家を売却した代金で、まずは残った住宅ローンを清算します。
その上で余剰があれば、その金額を夫婦で分割します。
夫婦どちらかが住み続ける場合
債権者(銀行など)との関係では、これまで通り、住宅ローンの名義人が支払いを続ける必要があります。
このとき、離婚後の住宅ローンの負担割合について夫婦間で協議し、合意することは可能です。調停(財産分与調停または離婚調停)においても、このような合意は可能です。
ただし、この合意はあくまでも夫婦間での負担割合を決めるものです。債権者(銀行など)はこれまで通り、契約上の名義人に対し、住宅ローンの支払いを求めることができます。
お気軽にご相談ください
なるべく少ない負担で公平な解決を図るため、財産分与についてはお早めに弁護士へご相談ください。